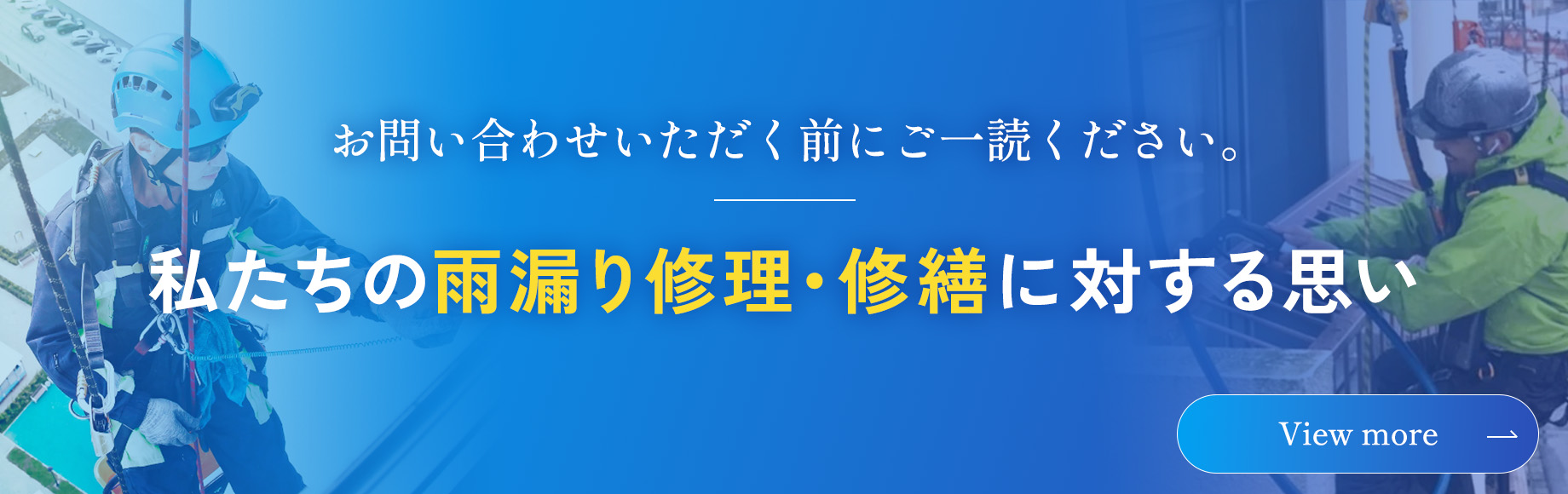サッシの雨漏りの原因を徹底解説|自分でできるチェック方法と対処法

窓からの雨漏りに悩まされている方は多く、特にサッシ部分からの浸水は見落とされやすいトラブルの一つです。
サッシの雨漏りは早期発見と適切な対処が重要で、放置すると建物の構造にまで悪影響を与える可能性があります。
この記事では、サッシの雨漏りの原因やチェック方法、対処法、予防策までをわかりやすく解説します。
サッシの雨漏りの原因はどこから?まず知っておきたい基本知識

まずは、サッシとは何か、雨漏りがどういう状態かを理解することが大切です。
サッシとは窓のフレーム部分のこと
サッシとは、窓ガラスを囲んでいるフレーム(枠)のことを指します。アルミや樹脂などの素材で作られていて、ガラスをしっかり固定する役割を持っています。
窓は外の空気や雨風を防ぐ大事な部分ですが、その縁となるサッシの構造が不完全だと、そこから水が入りやすくなります。
また、サッシは建物の外壁と接しているため、雨水の影響を直接受けやすい場所でもあります。
このサッシまわりに不具合があると、室内への雨漏りにつながります。
サッシの雨漏りは外からの水が室内に入ること
サッシからの雨漏りとは、雨が外壁や窓周りから室内へと浸入する現象です。
水は小さなすき間や亀裂からでも入り込むため、目に見える穴がなくても油断はできません。
雨の日に窓の下側が濡れていたり、壁紙にシミができていたりするなら、サッシの雨漏りが原因かもしれません。
特に長時間雨が降る日や、強風をともなう大雨のときに起こりやすいです。
雨漏りは建物の構造にも悪影響を与える
サッシの雨漏りを放置すると、柱や壁の中まで水が染み込み、建物の劣化が進む恐れがあります。
木造住宅の場合、柱が腐ったりカビが発生したりする原因になります。
また、断熱材が濡れると断熱性能が下がり、湿気による健康被害(ぜんそくやアレルギー)につながることもあります。
小さな水漏れでも、長期間続くと大きなトラブルになる可能性があります。
よくあるサッシの雨漏りの原因とその特徴
サッシの雨漏りにはさまざまな原因がありますが、特に多いパターンを知っておくことで予防や早期発見が可能です。
コーキング(シーリング)の劣化
窓のまわりには、防水のためのコーキング(またはシーリング)というゴム状の素材が使われています。
このコーキングは時間とともに劣化し、ひび割れたり縮んだりします。
そのすき間から水が入り込んで、室内に雨漏りが起きてしまうのです。
特に築10年を過ぎた家では、このコーキングの劣化が雨漏りの原因になることが多いです。
サッシ周りの防水シートの破れ
外壁と窓の間には、防水シートという水の侵入を防ぐ素材が入っています。
これが工事中の施工不良や経年劣化で破れていると、サッシから水が入りやすくなります。
防水シートの不具合は見た目では分かりにくく、専門業者による調査が必要な場合もあります。
築年数が経っている家では、注意が必要です。
窓枠と壁のすき間への水の侵入
サッシと外壁の間にわずかなすき間があると、そこから水が入り込みます。
特に強風時には、雨が吹き込むことで水が逆流しやすく、室内に染み込んでくることがあります。
サッシと外壁の接合部分にヒビや隙間がある場合は、早めに補修しましょう。
このような状態を放置すると、雨漏りの被害が拡大します。
強風を伴う雨による雨水の逆流
通常であれば防げる程度の雨でも、風の強い日には雨水が逆流してサッシの内側に入ることがあります。
この現象は「吹き込み」とも呼ばれ、特に台風シーズンに多く見られます。
サッシの構造によっては、水の排出口が小さく、逆流が起きやすいこともあります。
防げる構造に変えるか、こまめな清掃が効果的です。
ドレン(排水口)の詰まりで水があふれる
サッシの下には、「ドレン」と呼ばれる水を外に逃がす小さな排水口があります。
このドレンにゴミやホコリ、虫の死骸などが詰まると、水がうまく排出されずにあふれてしまいます。
その結果、サッシの内側に水が流れ込み、雨漏りにつながるのです。
定期的な掃除が必要です。
サッシの雨漏りの原因を自分でチェックする方法

雨漏りは専門業者に頼まなくても、ある程度なら自分で原因を調べることができます。以下に簡単なチェック方法を紹介します。
雨の日に窓まわりをよく観察してみる
雨が降っているときこそ、雨漏りの原因を見つけるチャンスです。
サッシの周囲や壁紙、床が濡れていないか注意して観察してみましょう。
水の染みや壁紙の浮きがあれば、そこが雨漏りの可能性が高いです。
気づいたら写真を撮っておくと、後から原因究明に役立ちます。
水を少しずつかけて漏れる場所を探す
晴れた日でも、ホースなどで水をかけてチェックする方法があります。
少しずつ水をかけながら、どの場所で漏れてくるかを観察します。
コーキングの割れ目やサッシの角など、水が入り込みやすい場所を重点的に確認しましょう。
ただし、家にダメージを与えないように、少量ずつ慎重に行ってください。
コーキングにひび割れやはがれがないか見る
外から見える範囲で、コーキングの状態をチェックしてみましょう。
ひび割れ、はがれ、剥離(はくり)などがあれば、そこから水が入ってくる可能性があります。
触ってみて硬くなっていたり、ぽろぽろと崩れたりする場合は、劣化が進んでいます。
新築から10年を超える場合は、点検のタイミングといえます。
室内の壁紙にシミができていないか確認する
室内の壁や天井、サッシまわりの壁紙にシミができていないかを確認します。
濃い色のシミ、触ると湿っている箇所は、雨漏りの疑いがあります。
シミが日に日に広がっている場合は、放置せず早急に対処が必要です。
乾いたら跡が残る場合もあるので、定期的にチェックしましょう。
サッシ下の排水穴(ドレン)をチェックする
ドレンは小さく見逃しやすいですが、ゴミや虫が詰まっていると排水ができずに逆流します。
歯ブラシや綿棒などを使って、やさしく掃除してみてください。
排水穴の中に水がたまっている場合は、詰まりのサインです。
雨のたびに水があふれるようであれば、要注意です。
サッシの雨漏りの原因を特定した後の対処法
雨漏りの原因が特定できたら、その場所に応じた正しい対処を行うことが大切です。自分でできる簡単な修理から、専門業者に依頼すべきケースまで、状況に合わせて判断しましょう。
劣化したコーキングを自分で打ち直す
コーキングのひび割れやはがれが原因の場合は、古いコーキングを除去し、新しく打ち直すことで防水性を回復できます。
ホームセンターでは「防水シーラント」や「変成シリコン」など、住宅用のコーキング材が手に入ります。
カッターやヘラを使って古いコーキングを丁寧に取り除き、マスキングテープで養生した後、新しいコーキングを打ちましょう。
施工後は24時間程度の乾燥が必要です。
防水テープで一時的に補修する
応急処置として便利なのが「防水テープ」です。水が入りやすいすき間やひびに貼るだけで、一時的に雨の侵入を防げます。
特に台風や長雨が続く前に応急処置をしておきたいときに有効です。
ただし、防水テープはあくまで一時的な対処法であり、長期的にはきちんとした補修が必要です。
テープが劣化すると逆に水が入りやすくなることもあります。
ドレンのゴミを取り除いて排水をよくする
サッシの下にある排水穴(ドレン)に詰まりがある場合は、中のゴミやほこりを取り除いて排水機能を回復させましょう。
細長いブラシや綿棒などを使って、奥まで優しく掃除します。
こまめに掃除することで、雨の日の逆流や水たまりを防げます。
掃除後は実際に水を流してみて、スムーズに排水されるか確認しましょう。
ホームセンターで買える補修材を使う
コーキング材以外にも、ホームセンターには便利な防水補修グッズが販売されています。
たとえば、「防水パテ」「シールタイプの防水シート」「外壁用補修スプレー」などが代表的です。
自分で補修する際は、説明書をよく読み、正しい使い方で施工することが大切です。
気になる場所に使って、雨漏りを一時的に防ぐ効果があります。
被害が大きいときは専門業者に連絡する
自分での対応に限界を感じたら、早めにリフォーム会社や防水業者などの専門業者に相談しましょう。
特に壁の中や天井まで水が染みているような場合は、自分での修理では対応できません。
プロの点検によって正確な原因が特定され、建物の構造まで含めた修理が可能です。
相見積もりを取って、信頼できる業者を選ぶこともポイントです。
業者に頼むべきサッシの雨漏りの原因とは?見極めのポイント

すべての雨漏りが自分で直せるわけではありません。以下のようなケースでは、専門の知識と技術が必要になるため、早めに業者に依頼することが重要です。
何度も同じ場所から雨漏りしている
一度修理してもまた雨漏りが再発する場合は、表面だけの処置では原因を完全に取り除けていない可能性があります。
根本的な防水層の劣化や施工不良が原因であることも考えられます。
同じ場所で繰り返す雨漏りは、早めに専門業者に相談すべきサインです。
何度も修理するよりも、一度の本格的な修理のほうが結果的に安く済むこともあります。
室内の壁や床にまで被害が広がっている
サッシまわりだけでなく、壁紙、床、天井まで被害が広がっている場合は早急な対処が必要です。
雨水が構造体や断熱材まで到達している可能性があり、健康被害や建物全体の耐久性に関わってきます。
このような場合、早めの調査と補修が建物を守ることにつながります。
補修後の乾燥や消臭処理が必要なケースもあります。
サッシの内部や壁の中が原因の場合
目に見えない場所に原因がある場合、自分での確認や修理は難しくなります。
サッシの内部や、外壁材の下にある防水シート、構造材などが原因の場合は、外壁の一部を解体して修理する必要があるため、専門業者の出番です。
無理に自分で解体すると、被害が広がる恐れもあります。
安心・安全のためにも、信頼できるプロに依頼しましょう。
自分で補修しても改善しない
コーキングを打ち直したり、防水テープを貼ったりしても雨漏りが止まらない場合は、自分の修理ではカバーできていない範囲に原因がある可能性が高いです。
誤った場所を修理してしまうと、労力も材料費も無駄になってしまいます。
早めに専門家の点検を受けることで、無駄な時間や費用を減らすことができます。
「なんとなく直った気がする」は危険なので、注意しましょう。
築10年以上経っている家で劣化が進んでいる場合
築10年以上経つと、外壁やサッシ周辺の部材が自然と劣化してきます。
コーキングの寿命も約10年前後とされているため、雨漏りがなくても一度専門点検を受けるのがおすすめです。
早めの補修が、将来の大きな修理費用を防ぐことにもつながります。
大切な家を長持ちさせるための定期メンテナンスと考えましょう。
サッシの雨漏り原因を防ぐための日ごろの予防法
日ごろのちょっとした点検や掃除が、サッシからの雨漏りを未然に防ぐカギになります。以下に簡単にできる予防法をまとめました。
定期的にコーキングの状態を確認する
外から見える範囲で、コーキングにひび割れやはがれがないか確認しましょう。
特に窓の四隅やサッシと壁の境目は注意が必要です。
早めに補修すれば、大きな雨漏り被害を防げます。
1年に1回は点検する習慣をつけましょう。
窓のまわりをこまめに掃除する
砂ぼこりや花粉、虫の死骸などがたまりやすいサッシまわりを定期的に掃除することで、ドレン詰まりやすき間への水の侵入を防げます。
掃除の際に異変に気づくこともあるので、一石二鳥です。
柔らかいブラシや雑巾を使って、優しく掃除しましょう。
ドレン(排水穴)にゴミがたまらないようにする
排水穴が詰まっていると水が逆流し、サッシから水が漏れる原因になります。
水の流れを確認し、たまに掃除して詰まりを予防しましょう。
落ち葉や虫の死骸が入り込みやすい場所なので、季節の変わり目に確認するのがおすすめです。
専用のドレンカバーなども販売されています。
外壁とサッシのすき間を定期的に点検する
外壁とサッシの接合部分にヒビやすき間がないかを確認しましょう。
小さなひび割れでも、雨水の侵入には十分な経路になってしまいます。
築年数が経つほど、こうした劣化が進みやすいので、年に1〜2回は点検をおすすめします。
異常が見つかれば、防水材やコーキング材で早めに補修しましょう。
大雨や台風の後はサッシまわりを点検する
大雨や強風が吹いた後は、サッシまわりがダメージを受けやすくなっています。
目に見えない不具合が起きていることもあるので、台風明けには一度点検する習慣をつけましょう。
早期発見が被害の拡大を防ぎます。
異常があれば記録を残しておくと、後の修理に役立ちます。
まとめ|サッシの雨漏りの原因を知って早めに対処しよう

小さな不具合でも放置しないことが大切
サッシからの雨漏りは、小さなすき間やひび割れがきっかけで発生するケースが多いです。
「少しだけだから大丈夫」と放置していると、建物全体に影響が広がる可能性があります。
早めの発見・対処が大切です。
定期的なチェックと掃除で雨漏りを防げる
コーキングの点検や、サッシまわりの掃除、ドレンの確認など、日常のメンテナンスで雨漏りの多くは予防可能です。
1年に1回でもいいので、自宅の窓周りをじっくり見てみましょう。
ちょっとした意識が家を守る第一歩になります。
異常を見つけたら早めに専門業者に相談しよう
自分で対処できないと感じたときや、被害が広がっていると感じたときは、迷わず専門業者に相談するのが安全です。
信頼できる業者に見てもらうことで、根本原因がわかり、安心して暮らせる住まいに戻せます。
大切な家を守るためにも、適切なタイミングでプロに頼る判断が重要です。
雨漏り調査、修繕はけんおうリノベーションにお任せください
雨漏りの調査や修理は、ぜひけんおうリノベーションにお任せください。
当社では、原因究明を完全成果報酬で行い、工事後には最低1年間の保証をお付けしています。さらに、目視検査や発光液、ガス検知を用いて、高精度な調査を実施しており、再発率は3%以下と非常に低いことが特徴です。
お見積りは無料で、追加料金も一切かかりませんので、ぜひ下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。