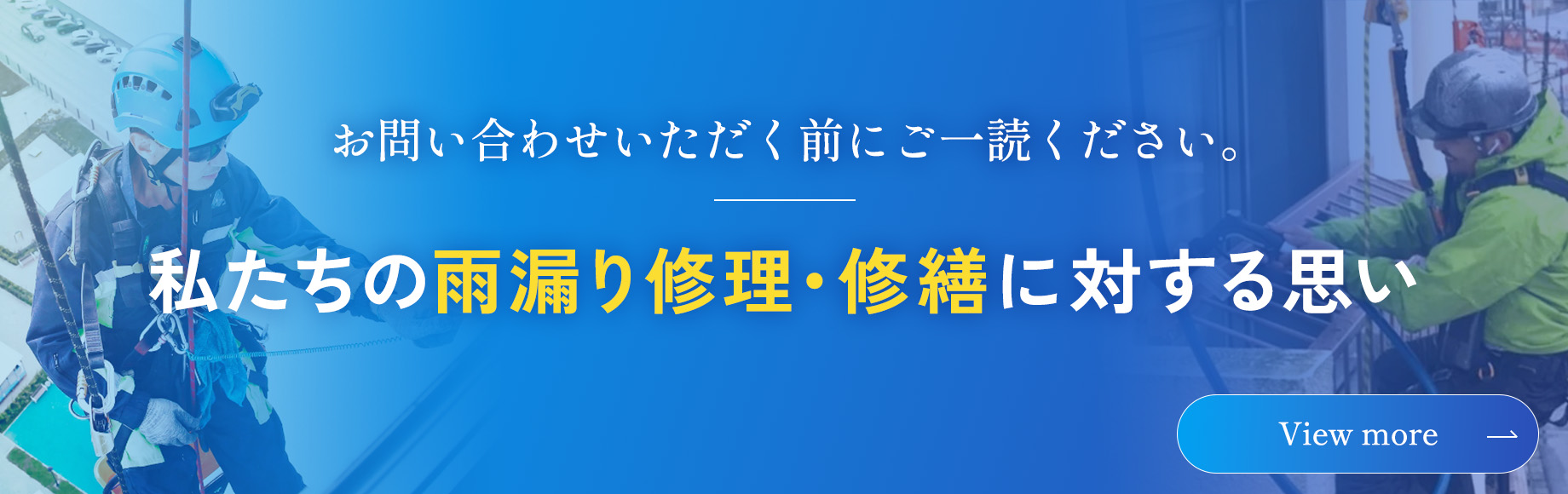1階の雨漏りの原因とは?見落とされがちな侵入経路と対策を徹底解説

「2階や屋根ならわかるけど、1階で雨漏りってどうして起こるの?」と思う方も多いのではないでしょうか。
実は、1階でもさまざまな原因で雨漏りは起きてしまいます。外壁のひび割れや配管のトラブル、床下からの浸水など、見落とされがちな要因がたくさんあります。
この記事では、1階の雨漏りに多い原因や注意すべきチェックポイント、早期発見・対策のポイントまで詳しく解説します。
1階で雨漏りが起こる原因とは?まず知っておきたい基本情報
まずは、1階で雨漏りが発生する主な原因についての基本を押さえましょう。
屋根だけでなく外壁や配管からも雨漏りは起きるから
雨漏りというと屋根から水がしみ込むイメージを持つ方が多いですが、実際には外壁や配管部分からも水が侵入することがあります。
特に1階の場合は、雨水が外壁の隙間や構造の継ぎ目から入り込むことで室内に漏れるケースが少なくありません。
また、外から見ても気づきにくい配管部分が原因になっていることもあります。
屋根以外の侵入口にも目を向けることが大切です。
築年数が経つと建物の防水性能が低下するから
建物は時間が経つと少しずつ劣化していきます。
特に、防水材やコーキング(すき間を埋めるためのゴム状の素材)は、10年前後で劣化することが多いです。
築年数が経った家では、これらの素材がひび割れてしまい、そこから雨水が入り込むことがあります。
定期的なメンテナンスを怠ると、雨漏りのリスクが高くなります。
地面に近い位置は雨水の跳ね返りや浸水の影響を受けやすいから
1階部分は、地面に近いため雨水が跳ね返って外壁に当たったり、地面からの浸水を受けたりしやすい場所です。
特に強い雨や台風の時は、通常の水の流れとは違う方向から水が建物に入り込むこともあります。
このような場合、床や壁の下部からじわじわと水が染み出すような形で雨漏りが発生します。
気づきにくい分、被害が広がりやすい場所なので注意が必要です。
1階の雨漏りの原因になりやすい侵入経路とは?
次に、実際に雨水が侵入しやすい具体的な場所を見ていきましょう。
外壁とサッシの取り合い部分から雨水が入りやすい
外壁と窓枠(サッシ)の境目は、建物の中でも特に水が入り込みやすい部分です。
この部分のコーキングが劣化していたり、施工ミスがあったりすると、そこから水が侵入します。
窓の下枠にシミができていたり、雨の日に窓の下が濡れていたら注意が必要です。
定期的にサッシまわりを確認し、ひび割れや劣化がないかをチェックしましょう。
換気口や配管の貫通部分が劣化して隙間ができやすい
建物の外壁には、エアコンや換気扇などのための穴が開いています。
これらの貫通部分は、コーキングやカバーで防水処理されていますが、時間が経つと劣化して隙間ができてしまうことがあります。
その小さな隙間から水が入り込み、壁の中を通って室内に達する場合もあります。
特に強風を伴う雨では、このような隙間から雨水が押し込まれることもあるので要注意です。
玄関ドアまわりのコーキングが切れていることがある
玄関ドアまわりも雨水が侵入しやすい場所の一つです。
見た目ではわかりにくいですが、ドアの枠まわりの防水材が劣化して切れていると、そこから水がしみ込んでしまいます。
玄関の床が濡れていたり、ドア下の壁が湿っている場合は、雨漏りを疑ってみましょう。
コーキングの状態をチェックし、ひび割れや隙間があれば修理を検討しましょう。
1階の雨漏りの原因に多い外壁や窓まわりのチェックポイント

1階で雨漏りが起きやすい外壁や窓まわりについて、具体的にチェックすべきポイントを紹介します。
外壁のひび割れや浮きがあると雨水が浸入しやすい
外壁にできたひび割れは、雨水が入り込む「入り口」になります。
特に縦に長いひびや、深くえぐれたようなひび割れには注意が必要です。
また、塗装が浮いていたり剥がれていたりする部分も、内部に水が浸透しやすい状態です。
外壁の状態は見た目である程度確認できるため、定期的な目視点検が効果的です。
窓枠まわりのコーキングの劣化が原因になることが多い
窓のまわりに使われているコーキングは、経年劣化しやすい部分です。
紫外線や雨風の影響で、コーキングが縮んだりひび割れたりすると、そこから水が侵入します。
コーキングの割れや剥がれが見つかったら、早めに打ち直すことが大切です。
DIYでも補修できますが、広範囲な劣化や雨漏りがある場合は業者に相談しましょう。
雨戸やシャッターBOXからの浸水が起こるケースがある
窓の上に取り付けられたシャッターBOXや雨戸の収納スペースも、雨漏りの原因になります。
内部にたまった水が適切に排出されず、建物内部にしみ込んでしまうことがあるためです。
また、取り付け部分の防水処理が不十分な場合も、浸水のリスクが高まります。
水のたまりや排水穴の詰まりがないか、定期的に確認しましょう。
1階の雨漏りの原因として見落としがちな床下や基礎の問題
目に見えにくい床下や基礎部分も、実は雨漏りの原因になることがあります。見落とされがちなポイントだからこそ、注意が必要です。
基礎のひび割れから雨水が侵入することがある
建物の土台である基礎にひびが入ってしまうと、そこから地面の水分や雨水がしみ込んでくることがあります。
特にコンクリート基礎に亀裂がある場合、その隙間から水が入り、床下が湿気でいっぱいになるケースも珍しくありません。
床下の湿気はカビや腐食の原因にもなるため、早めにチェックしましょう。
基礎にヒビを見つけた場合は専門業者に相談し、必要に応じて補修を行いましょう。
地面からの雨水の逆流が床下を通じて室内に侵入する
豪雨や台風のとき、雨水が排水できずに地面から逆流して床下へ流れ込むことがあります。
この場合、床板の隙間や配管のまわりから水が浸入し、室内の床が濡れてしまうことがあります。
排水設備の不具合や敷地の傾斜、排水マスの詰まりなどが原因です。
排水経路の確認や清掃も、雨漏り防止の一環として重要です。
排水管の破損や接合不良が床下に水を漏らしている場合がある
排水管のひび割れや接合部の不良も、1階の水漏れに繋がる大きな原因です。
雨水ではなくても、キッチンやお風呂、トイレの排水が床下で漏れてしまうと雨漏りと勘違いされることがあります。
長期間気づかずにいると、木材の腐食やカビの原因にもなります。
床下に異臭や湿気がある場合は、配管の状態を点検してみましょう。
1階の雨漏りの原因が室内設備にある場合とは?

雨が降っていないのに「雨漏りかも?」と思ったときは、室内設備のトラブルも疑ってみましょう。
エアコンのドレンホースの詰まりや漏れが原因になる
エアコンには、室内の湿気を外に排出するドレンホースがあります。
このホースが詰まっていたり、破損していたりすると、水が室内に逆流してしまうことがあります。
特にホースの出口が外壁近くにあり、そこから水が逆流して外壁を伝って建物内に侵入することもあります。
定期的にホースの状態を確認し、ゴミ詰まりなどがないように掃除しておきましょう。
給排水管の劣化や破損による水漏れが雨漏りと誤認されることがある
水道管や排水管の劣化による水漏れは、雨漏りと間違いやすいトラブルのひとつです。
特に天気に関係なく水が出てきたり、湿っていたりする場合は、給排水設備の異常を疑いましょう。
水漏れは雨漏りと違い、24時間いつでも起こるため、症状の出方にも注目が必要です。
設備業者による点検で原因をはっきりさせましょう。
洗面所・キッチンの接続部からの漏れが壁や床に広がることがある
キッチンや洗面台の下の配管部分の接続不良から水が漏れることがあります。
その水が床や壁の内部を伝って染み込み、結果的に壁や床に雨漏りのような症状を起こすことがあります。
特に配管まわりのコーキングが切れていたり、ホースがずれていたりすると漏れやすくなります。
水回りの収納の中も定期的にチェックして、湿っていないか確認しましょう。
1階の雨漏りの原因を特定するための調査方法とは
雨漏りが起きたときは、まず原因を正しく突き止めることが重要です。ここでは一般的な調査方法を紹介します。
散水調査で実際に水をかけて漏れ箇所を確認できる
専門業者がホースで建物の外壁や窓まわりに水をかけて調べる方法です。
実際に雨が降ったときのような状況を再現できるため、どこから水が入るかを確認するのに効果的です。
ただし、完全な特定には時間がかかる場合もあるため、天候や状況に合わせて実施されます。
散水調査は比較的安価で、初期診断としてよく使われます。
赤外線カメラで温度差から漏水箇所を可視化できる
水がたまっている部分は温度が低くなるため、赤外線カメラを使えば水の通り道が見えてきます。
目に見えない場所の漏水も発見できるのが大きなメリットです。
雨漏りが止まっている状態でも、過去の浸水の痕跡をたどることができます。
費用はかかりますが、正確な原因特定に役立ちます。
点検口や床下からの目視調査で基礎内部の状況を確認できる
床下に点検口がある場合、実際に中に入って水の侵入状況や配管の破損を確認します。
シロアリやカビの被害も同時にチェックできるため、建物全体の健康状態が把握できます。
床下の異常は、外からではわかりにくいため、プロによる調査が安心です。
年に一度の点検を習慣にすることで、大きな被害を防ぐことができます。
1階の雨漏りの原因ごとの対策法と修理費用の目安

それぞれの原因に応じた対策方法と、おおよその修理費用について解説します。
コーキングの打ち替えは数万円からできる
外壁や窓まわりのコーキングが劣化している場合は、部分的な打ち替えで対処できます。
費用は1か所あたり1〜3万円程度が相場で、DIYでも対応可能な範囲です。
ただし広範囲に渡る場合や、高所作業が必要な場合はプロに依頼しましょう。
早めの対処で被害の拡大を防げます。
外壁補修や防水工事は10万円〜50万円程度かかる場合がある
外壁のひび割れや塗装の浮きが原因の場合は、外壁全体の補修や再塗装、防水処理が必要になります。
施工範囲によって費用は大きく変わりますが、10万円〜50万円程度を見込んでおくと安心です。
家の耐久性を高めるためにも、予算を組んでしっかり修繕しましょう。
定期的な塗装メンテナンスが雨漏りの予防にもつながります。
基礎補修や排水設備の修理は業者によって費用が大きく異なる
基礎部分のひび割れや排水トラブルは、場所や被害の大きさによって工事の規模や費用が大きく変わります。
軽微な補修なら数万円程度で済みますが、大規模な場合は数十万円以上かかることもあります。
複数の業者から見積もりを取り、内容を比較することが大切です。
信頼できる専門業者を選ぶことが、安心につながります。
1階の雨漏りの原因を放置するとどうなる?放置リスクと被害例
1階の雨漏りを放っておくと、健康面・建物面ともに深刻なトラブルにつながります。ここではその主なリスクを3つに分けて紹介します。
木材の腐食やカビの発生で健康被害が出るおそれがある
雨漏りによって水が建物の内部にしみこむと、柱や壁の中の木材が湿気を含み、やがて腐食していきます。木材が腐ることで、建物の強度が弱くなるだけでなく、腐った部分にカビが発生しやすくなります。
カビは、アレルギーや喘息、皮膚炎などの健康被害を引き起こす原因となります。
特に、小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、健康リスクが高くなるため注意が必要です。
また、湿った場所はダニや害虫の温床にもなりやすく、衛生面でも悪影響を及ぼします。
目に見えない場所でカビが進行するため、「気づいたときには被害が広がっていた」というケースも少なくありません。
白アリを呼び込み家の構造が弱くなる可能性がある
雨漏りで湿気がたまった場所は、白アリにとって格好の住処となります。白アリは湿った木材を好んで食べるため、放置しておくと柱や土台など、家の重要な構造部分が食い荒らされてしまうことがあります。
一度白アリが発生すると、駆除には時間と費用がかかるうえ、建物の耐震性にも影響を及ぼします。
特に1階部分は基礎に近く、白アリの侵入経路となりやすいため、雨漏りが引き金となって白アリ被害が拡大するケースが多くあります。
雨漏りと白アリはセットで発生することがあるため、片方だけでなく両方を対策する意識が大切です。
修理費が高額になる前に早期対処が必要
雨漏りを初期の段階で見つけて修理すれば、数万円〜十数万円程度で済む場合が多いです。しかし、放置することで被害が広がると、修理範囲が拡大し、費用も跳ね上がってしまいます。
例えば、壁の内部にカビが広がっていた場合、壁の一部を壊して内部の断熱材や木材を交換しなければならないこともあります。
さらに、白アリの被害が出ていれば、駆除・防除・構造補修が必要となり、工事費用は数十万円〜数百万円に膨らむ可能性もあります。
費用だけでなく、工期も長引き、その間の生活に支障が出ることもあるため、早期発見と対処が非常に重要です。
1階の雨漏りの原因を防ぐためにできる日常のメンテナンス

1階の雨漏りを防ぐには、日ごろからの点検やお手入れが欠かせません。ここでは、誰でも簡単にできる日常のメンテナンス方法を紹介します。
外壁や窓まわりのコーキングの状態を定期的に確認する
雨漏りの原因で多いのが、外壁や窓のまわりに使われている「コーキング材(シーリング)」の劣化です。コーキングとは、隙間から雨水が入らないようにするゴムのような素材のことです。
このコーキング材は、紫外線や雨風の影響で少しずつ劣化し、ひび割れたり、剥がれたりすることがあります。
年に1回程度、窓のふちや壁のつなぎ目を目視でチェックし、ひび割れや隙間がないかを確認しましょう。
劣化が見られたら、専門業者に依頼して打ち替えてもらうことをおすすめします。
排水口やドレンの詰まりを掃除しておく
ベランダやバルコニー、屋根の排水口やドレンに落ち葉やゴミが詰まっていると、水がうまく流れず、たまった雨水が建物内部に浸入するリスクがあります。
特に台風や大雨の後は排水口が詰まりやすくなるため、定期的な掃除が重要です。
掃除はゴム手袋とビニール袋を使って、手でゴミを取り除くだけでも効果的です。
月に1回程度の簡単なチェックを習慣にするだけで、大きなトラブルを未然に防げます。
定期的に専門業者に点検を依頼する
自分で点検するだけでは見つけにくい雨漏りの原因もあります。特に、屋根裏や壁の内部などは、専門的な知識と道具がないと正確なチェックが難しい箇所です。
そのため、年に1回程度は専門業者による定期点検を受けることをおすすめします。
プロの点検では、赤外線カメラなどを使って目に見えない水の流れを確認できるため、早期発見につながります。
また、メンテナンス履歴を残しておくことで、万が一保険請求が必要になった際にも有利になります。
まとめ|1階の雨漏りの原因を正しく知って早めに対策しよう
1階の雨漏りは、見逃しやすく放置しがちですが、実は建物と健康の両方に大きなリスクをもたらします。カビや腐食、白アリの被害は、早めに対処しなければ深刻な問題へと発展します。
日常的にできる点検やお手入れを習慣にすることで、雨漏りを未然に防ぐことが可能です。外壁のコーキング、排水口の掃除、そしてプロの点検をうまく活用しましょう。
「ちょっとした水漏れだから」と軽く考えず、早期発見・早期対応を心がけることで、大切な家を長く安心して使い続けることができます。
もし少しでも気になる症状がある場合は、早めに専門業者に相談してみてください。
雨漏り調査、修繕はけんおうリノベーションにお任せください
この記事では、1階の雨漏りに多い原因などについて詳しくご紹介しました。この記事を読んで、雨漏りの原因調査や修理が必要だと感じた方も多いのではないでしょうか。
雨漏りの調査や修理は、ぜひけんおうリノベーションにお任せください。
当社では、原因究明を完全成果報酬で行い、工事後には最低1年間の保証をお付けしています。さらに、目視検査や発光液、ガス検知を用いて、高精度な調査を実施しており、再発率は3%以下と非常に低いことが特徴です。
お見積りは無料で、追加料金も一切かかりませんので、ぜひ下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。